News
- 学生表彰:学部生・川上 夕君が,2022年度の研究科長表彰(自然科学学生奨励賞)を受賞しました
- 学生表彰:修士課程・小畠 美穂君が,2021年度の研究科長表彰(自然科学学生奨励賞)を受賞しました
- 学生表彰:学部生・三好亜紀君が,2021年度の学部長表彰(応用理数学生奨励賞)を受賞しました
- 学生表彰:学部生・田中 功君が, 徳島大学応用理数コースから2020年度コース表彰を受賞しました
- 上野雅晴 講師が、准教授に昇任しました
- 上野 雅晴 講師が、研究代表者・科学研研究費補助費・基盤研究(C)2019.4-2022.3の助成を受けています
- 学生表彰:学部生・小畠 美穂君が, 徳島大学応用理数コースから2019年度コース表彰を受賞しました
最新の注目研究 (太字は学生)
- Masaharu Ueno, Kusaka Ryo, Satoshi D. Ohmura and Norikazu Miyoshi: Environmentally Benign Ritter Reaction Using Bismuth Salt as a Catalyst, European Journal of Organic Chemistry, Vol.2019, No.8, 1796-1800, 2019. (Cite Score2018 2.81)
- Naoki Nakao,Masaharu Ueno, Shota Sakai, Daich Egawa, Hiroyuki Hanzawa, Shohei Kawasaki, Keigo Kumagai, Makoto Suzuki, Shu Kobayashi and Kentaro Hanada : Natural ligand-nonmimetic inhibitors of the lipid-transfer protein CERT.,Communications Chemistry,Vol.2, Articlenumber:20, 2019. (N.N., M.U., and S.S. equally contributed to this study and are the co-first authors), (Field-Weighted Citation Impact 2.56)
研究概要
1. 金属ストロンチウムを用いる新規かつ新奇機能性物質の簡便合成

ストロンチウム(Sr)は地殻存在比が比較的高い第2族(アルカリ土類金属)第5周期に位置する原子番号38の元素である。そしてストロンチウム金属およびストロンチウム化合物は毒性もほとんどなく比較的安価であり、様々な化合物が市販されているが、有機合成反応に応用した報告例は数例しかない。このような観点から、ストロンチウム元素の独自で新たな性質を明らかにできるならば、有機合成化学のみならず元素戦略的にも有用と考え研究を行っている。その結果、下記に示すような種々の反応を見出した。これらの反応は、対応する同族元素であるマグネシウムを用いるGrignard試薬と比較検討すると、新たな新しい性質を持つことが判明した。例えば、イミンに関しては、t-Bu基の導入も可能である。エステルのジアルキル化においてはGrignard試薬を用いると進行しない、i-Bu基やneopentyl基も付加させることができる。さらに、本反応に酸塩化物を作用させると、非常に合成が困難な第3級アルコールのエステルを高収率に得ることが出来る。一方、カルボン酸に対しアルキル化を行うと、モノアルキル化されたケトンが比較的良好な収率で得られる。更に、安息香酸に対しては、異常反応が進行し、安息香酸のp-位にアルキル基が付加した生成物が高収率で得られることがわかった。修飾していない安息香酸へのp-アルキル化反応の例はなく、室温下での無保護のカルボン酸のモノアルキル化反応例もない。また最近、ストロンチウムアルコキシドが非常に強い求核性を持つことに着目し、通常では行えない嵩高いアルコールのアシル化、並びにシリル化を達成した。この様に、ストロンチウム反応剤は、従来法とは異なる反応性を示すことが明らかになった。この知見を基に、新規かつ新奇な機能性物質の合成を試みている。
2. 多成分タンデムカップリング反応の開発とフロー合成への展開

医薬品やファインケミカルに合成おいて多用されている、パラジウムをはじめとする触媒的なカップリング反応の効率化を目指し、一つの触媒・一つの反応容器で異なるカップリング反応を選択的かつ連続的に行い、多置換ビアリール化合物を一挙に合成する手法の確立を目指して研究を行なっています。将来的には触媒を担持剤に固定化し、環境中に漏れ出すことの無い固定化触媒の創製を行なっていきたいと考えています。そうすることにより、固定化触媒を筒状の容器(カラム)に詰め、原料を流せばカラムの中でカップリング反応が自動的に進行するフローケミストリーに展開できます。これは、触媒の低減化に繋がるばかりか、反応停止後の分液・精製操作を簡略化することができるため、理想的なグリーンケミストリーの実用例となります。
3. 人工設計した新たなセラミド輸送タンパク質阻害剤の開発
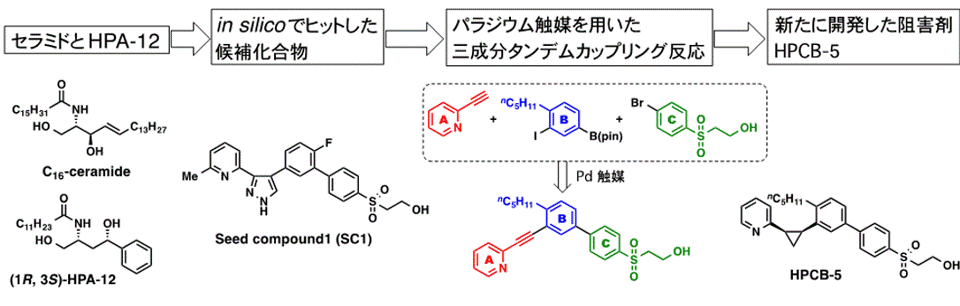
多成分タンデムカップリング反応を利用して、コンピューター解析で人工設計した新しいタイプのセラミド輸送タンパク阻害剤の開発を行なっています。 セラミドという言葉は化粧品や機能性食品のCM等で聞いたことがあるかもしれませんが、細胞内や細胞間のシグナル伝達物質の原料としても使われています。これまで私たちは哺乳動物細胞の小胞体ゴルジ体間でセラミド輸送を行なう、ある特定の輸送タンパクの阻害剤HPA-12を見いだしていました。この経路のセラミド輸送を阻害することで、抗感染症や抗がん治療への応用も期待出来ますが、HPA-12はセラミドと構造が似ているため、他のセラミド輸送タンパク経路を阻害してしまう(これをオフターゲット効果と言います)可能性が有ります。HPA-12によって阻害されたタンパク質の結晶構造を基に、HPA-12とは違う新たな阻害剤探索をコンピューター解析(これをin silicoスクリーニングと言います)したところ、ポリアリール構造を持つ化合物が候補としてヒットしてきました。そこで、多成分タンデムカップリング反応により中間体を大量供給し、分子変換反応により120種以上の類縁体を合成した結果、新たなセラミド輸送タンパク阻害剤HPCB-5の開発に成功しました。現在、より簡便な合成経路の確立、およびこのカップリング反応を利用する他の候補化合物の合成検討等を行なっています。